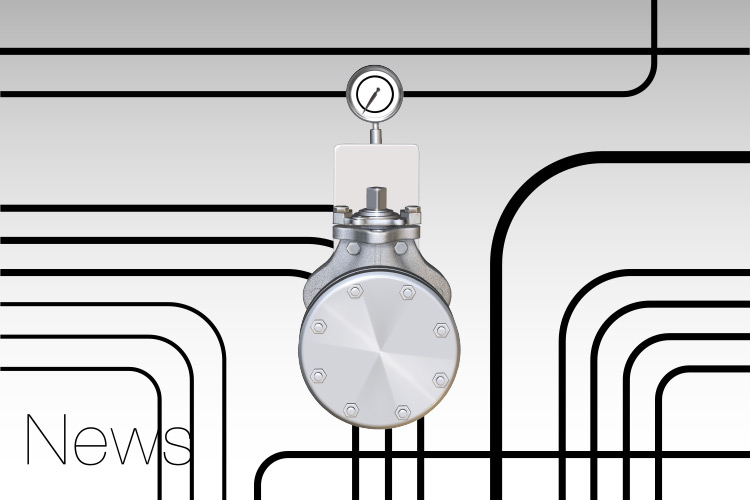日本タンクターミナル協会 宮川靖嘉 会長
タンクの供給量を増やす意思表示が必要
CN対応では「業界間競争」も意識
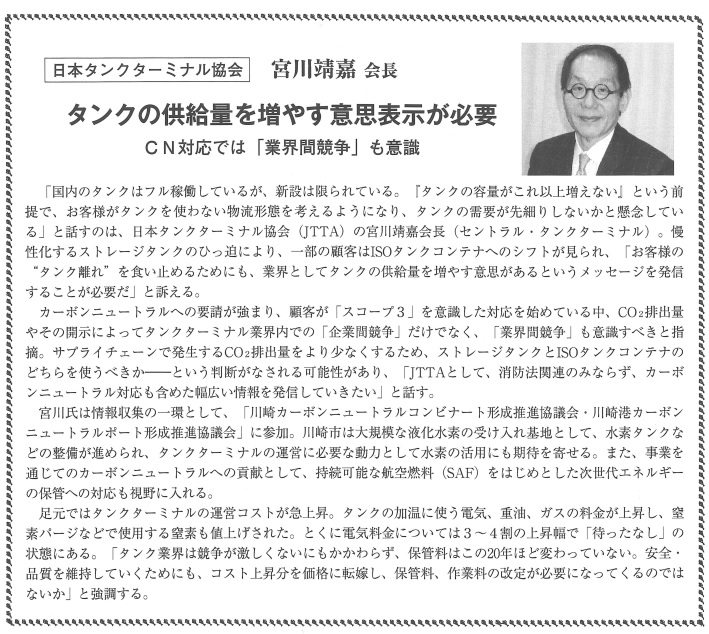
「国内のタンクはフル稼働しているが、新設は限られている。「タンクの容量がこれ以上増えない」という前提で、お客様がタンクを使わない物流形態を考えるようになり、タンクの需要が先細りしないかと懸念している」と話すのは、日本タンクターミナル協会(JTTA)の宮川靖嘉会長(セントラル・タンクターミナル)。慢性化するストレージタンクのひっ迫により、一部の顧客はISOタンクコンテナへのシフトが見られ、「お客様の“タンク離れ”を食い止めるためにも、業界としてタンクの供給量を増やす意思があるというメッセージを発信することが必要だ」と訴える。
カーボンニュートラルへの要請が強まり、顧客が「スコープ3」を意識した対応を始めている中、CO2 排出量やその開示によってタンクターミナル業界内での「企業間競争」だけでなく、「業界間競争」も意識すべきと指摘。サプライチェーンで発生するCO2排出量をより少なくするため、ストレージタンクとISOタンクコンテナのどちらを使うべきか―――という判断がなされる可能性があり、「JTTAとして、消防法関連のみならず、カーボンニュートラル対応も含めた幅広い情報を発信していきたい」と話す。
宮川氏は情報収集の一環として、「川崎カーボンニュートラルコンビナート形成推進協議会・川崎港カーボンニュートラルポート形成推進協議会」に参加。川崎市は大規模な液化水素の受け入れ基地として、水素タンクなどの整備が進められ、タンクターミナルの運営に必要な動力として水素の活用にも期待を寄せる。また、事業を通じてのカーボンニュートラルへの貢献として、持続可能な航空燃料(SAF)をはじめとした次世代エネルギーの保管への対応も視野に入れる。
足元ではタンクターミナルの運営コストが急上昇。タンクの加温に使う電気、重油、ガスの料金が上昇し、窒素パージなどで使用する窒素も値上げされた。とくに電気料金については3~4割の上昇幅で「待ったなし」の状態にある。「タンク業界は競争が激しくないにもかかわらず、保管料はこの20年ほど変わっていない。安全・品質を維持していくためにも、コスト上昇分を価格に添加し、保管料、作業料の改定が必要になってくるのではないか」と強調する。
カーボンニュートラルへの要請が強まり、顧客が「スコープ3」を意識した対応を始めている中、CO2 排出量やその開示によってタンクターミナル業界内での「企業間競争」だけでなく、「業界間競争」も意識すべきと指摘。サプライチェーンで発生するCO2排出量をより少なくするため、ストレージタンクとISOタンクコンテナのどちらを使うべきか―――という判断がなされる可能性があり、「JTTAとして、消防法関連のみならず、カーボンニュートラル対応も含めた幅広い情報を発信していきたい」と話す。
宮川氏は情報収集の一環として、「川崎カーボンニュートラルコンビナート形成推進協議会・川崎港カーボンニュートラルポート形成推進協議会」に参加。川崎市は大規模な液化水素の受け入れ基地として、水素タンクなどの整備が進められ、タンクターミナルの運営に必要な動力として水素の活用にも期待を寄せる。また、事業を通じてのカーボンニュートラルへの貢献として、持続可能な航空燃料(SAF)をはじめとした次世代エネルギーの保管への対応も視野に入れる。
足元ではタンクターミナルの運営コストが急上昇。タンクの加温に使う電気、重油、ガスの料金が上昇し、窒素パージなどで使用する窒素も値上げされた。とくに電気料金については3~4割の上昇幅で「待ったなし」の状態にある。「タンク業界は競争が激しくないにもかかわらず、保管料はこの20年ほど変わっていない。安全・品質を維持していくためにも、コスト上昇分を価格に添加し、保管料、作業料の改定が必要になってくるのではないか」と強調する。
(2023/5/30 カーゴニュース 掲載)