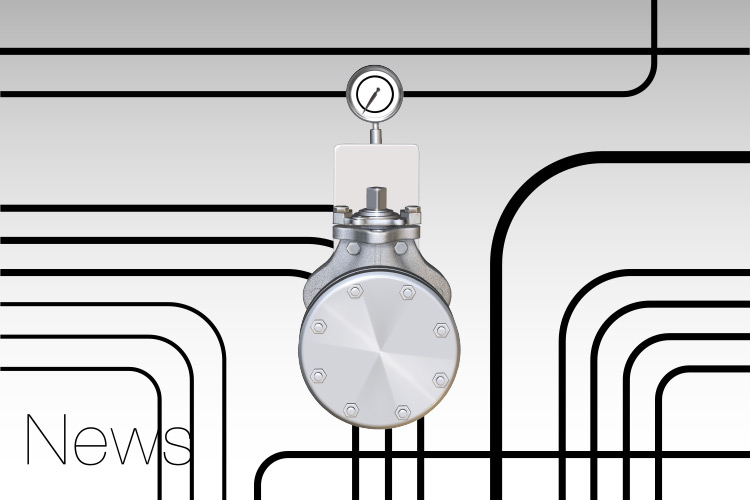タンクターミナル構内での物流加工作業に付加価値を
長年蓄積してきたノウハウと品質で差別化 JTTA 小幡柾夫会長

「全国的にタンクの成約率は高水準で、中にはすべて埋まっているという会社もある。輸入品が増えたことと、国内メーカーの定修等のスポット需要も堅調であることが背景として挙げられる。また、タンクを借りる前段階の小ロットの輸入で、ISOタンクコンテナからローリー、ドラム缶等への詰め替えなどの作業の引き合いも増えている」と話すのは、日本タンクターミナル協会(JTTA)の小幡柾夫会長。“マルチワークステーション”などの名称で呼ばれる消防法上の「一般取扱所」を活用した物流加工作業の需要がタンクターミナル業界で急増している。
こうした物流加工作業については昨今の需要増を受けて、危険物倉庫やISOタンクコンテナを運用する物流会社など、タンクターミナル以外の業態からも参入があり、「タンクターミナル構内で物流加工作業を行うことの付加価値を高めていかなければならない」と指摘。タンクターミナルのアドバンテージとして、「引火点が低い、粘度が高い、においがきついなど取り扱いが難しい液体危険物については、バルクの液体危険物を扱うタンクターミナル事業者は長年蓄積してきたノウハウがある。ノウハウと品質で差別化していきたい」と語る。
JTTAの活動では、6月には関連業界である内航タンカー組合ケミカル委員会と交流会を開催。タンクターミナルとタンカーは液体貨物の荷揚げ、荷下ろし時に重要な接点があり、「今後は情報交換と連携を密にし、要望活動などを共同で行っていくことも検討したい」。また、10月には、総会開催を兼ねてタイ視察を計画。バンコクで代表的な2つのエリアにある会員企業のタンクターミナルを見学する予定だ。「JTTAは以前にもシンガポール、韓国、台湾で海外視察を行った。こうした機会を利用し、若いうちに海外に行って自分の目で見て見分を広め、刺激を受けてほしい」と話す。
業界にとって最大の課題は安全対策。液体危険物を大量に扱うタンクターミナル業界は「そこまでやるか」と言われるほど、安全関連に先行投資しており、「設備が古くなって使えなくなりそうだから、(設備更新に)重たい腰を上げる――という会社は1社もない」。一方、「IT化、機械化により、昔のように先輩から手取り足取り仕事を教えてもらい、経験で覚えることが少なくなっている。物流加工作業のノウハウも含めて、先輩のやり方を見ながら、“実学”で学ぶこと、ベテラン社員による教育の仕組みづくりが重要になってくる」と話す。
(2013/7/16カーゴニュース紙掲載)
こうした物流加工作業については昨今の需要増を受けて、危険物倉庫やISOタンクコンテナを運用する物流会社など、タンクターミナル以外の業態からも参入があり、「タンクターミナル構内で物流加工作業を行うことの付加価値を高めていかなければならない」と指摘。タンクターミナルのアドバンテージとして、「引火点が低い、粘度が高い、においがきついなど取り扱いが難しい液体危険物については、バルクの液体危険物を扱うタンクターミナル事業者は長年蓄積してきたノウハウがある。ノウハウと品質で差別化していきたい」と語る。
JTTAの活動では、6月には関連業界である内航タンカー組合ケミカル委員会と交流会を開催。タンクターミナルとタンカーは液体貨物の荷揚げ、荷下ろし時に重要な接点があり、「今後は情報交換と連携を密にし、要望活動などを共同で行っていくことも検討したい」。また、10月には、総会開催を兼ねてタイ視察を計画。バンコクで代表的な2つのエリアにある会員企業のタンクターミナルを見学する予定だ。「JTTAは以前にもシンガポール、韓国、台湾で海外視察を行った。こうした機会を利用し、若いうちに海外に行って自分の目で見て見分を広め、刺激を受けてほしい」と話す。
業界にとって最大の課題は安全対策。液体危険物を大量に扱うタンクターミナル業界は「そこまでやるか」と言われるほど、安全関連に先行投資しており、「設備が古くなって使えなくなりそうだから、(設備更新に)重たい腰を上げる――という会社は1社もない」。一方、「IT化、機械化により、昔のように先輩から手取り足取り仕事を教えてもらい、経験で覚えることが少なくなっている。物流加工作業のノウハウも含めて、先輩のやり方を見ながら、“実学”で学ぶこと、ベテラン社員による教育の仕組みづくりが重要になってくる」と話す。
(2013/7/16カーゴニュース紙掲載)